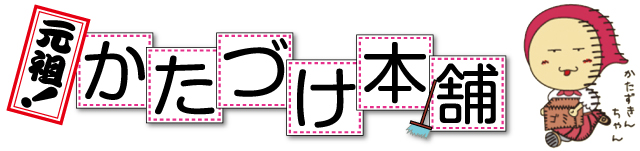第3章:【自宅編】40代が今すぐ始める整理術
自分の家の「介護対応力」診断
実家の片付けばかりに気を取られて、自分の家のことを忘れていませんか?
親の介護が始まった時、あなたの家は「介護を支える基地」になります。しかし、その基地が整っていなければ、介護生活は破綻します。
まずは、あなたの家の「介護対応力」を診断してみましょう。
【診断チェックリスト】
以下の項目に、正直にチェックを入れてください。
▼スペース編
- □ 親の荷物を一時保管できるスペースがある(クローゼットや押し入れの一角)
- □ 玄関から寝室まで、車椅子が通れる幅がある(80cm以上)
- □ 万が一、親を自宅で介護することになった場合、介護ベッドを置けるスペースがある
- □ 廊下や階段に、モノが置かれていない
- □ 家族全員の靴が、玄関にきちんと収納されている
▼書類・情報管理編
- □ 重要書類(保険証、年金手帳、通帳、印鑑、権利証等)がすぐに取り出せる
- □ 家族全員の健康保険証と診察券が、1箇所にまとまっている
- □ 契約書類(携帯、光熱費、保険、ローン等)がファイリングされている
- □ パスワード管理ができている(銀行、カード、各種サービス)
- □ 緊急連絡先リストが作成されている
▼家族対応編
- □ 1週間家を空けても、家族が困らない状態(食事、洗濯、掃除ができる)
- □ 夫や子どもが、家の中のモノがどこにあるか把握している
- □ 「もしもの時」について、家族で話し合ったことがある
- □ 自分が倒れた時の対応を、家族が知っている
▼精神的余裕編
- □ 探し物をすることが、ほとんどない
- □ 週に1回以上、家をすっきりと掃除できている
- □ 友人や親戚が突然訪ねてきても、家に上げられる
- □ 自分の「好きなもの」だけに囲まれている
- □ 家にいると、心が落ち着く
【診断結果】
チェックが15個以上:介護対応力◎ 素晴らしいです!あなたの家は、いつ介護が始まっても対応できる状態です。この状態を維持しつつ、定期的な見直しを続けましょう。
チェックが10〜14個:介護対応力○ 基本的な整理はできていますが、まだ改善の余地があります。特にチェックが入らなかった項目を、優先的に改善しましょう。
チェックが5〜9個:介護対応力△ 要注意です。このままでは、介護が始まった時に困ります。今すぐ、この章で紹介する整理術を実践しましょう。
チェックが4個以下:介護対応力× 危険信号です!今すぐ整理を始めないと、介護が始まった時にパンクします。まずは、最優先事項から手をつけましょう。
診断結果はいかがでしたか?
もし、チェックが少なかったとしても、落ち込む必要はありません。今気づけたことが、何よりも大切なのです。
これから、具体的な整理術をお伝えしていきます。一つずつ、できることから始めていきましょう。
40代の「捨てどき」判断術
40代は、人生の大きな転換期です。
子どもは成長し、親は高齢化し、自分自身も体力の変化を感じ始める――。そんな時期だからこそ、「モノとの付き合い方」を見直すタイミングなのです。
しかし、「捨てられない」と悩む人も多いでしょう。
「いつか使うかも」「もったいない」「思い出があるから」――。
そんなあなたのために、40代の「捨てどき」を判断する基準をお伝えします。
基準1:子どもの成長と共に不要になるもの
子どもが成長すると、必要なものは変わります。しかし、「思い出」に縛られて、いつまでも取っておいていませんか?
すぐに処分すべきもの
- ベビー用品(ベビーベッド、ベビーカー、チャイルドシート) → もう一人産む予定がなければ、すぐに処分。知人に譲る、フリマアプリで売る、寄付する。
- サイズアウトした子ども服 → 「思い出の1枚」だけ残して、あとは処分。写真に撮って記録するのもおすすめ。
- 使わなくなったおもちゃ → 子どもと一緒に選別。「1年遊んでいないもの」は処分対象。
- 小学校の教材・プリント類 → テストは最新の1学期分だけ。作品は写真に撮って処分。
- 塾のテキスト・参考書 → 受験が終わったら、すぐに処分。「弟妹が使うかも」は、ほぼ使いません。
判断のコツ
「もう一度使うか?」ではなく、「この1年で使ったか?」で判断します。
使っていないものは、今後も使いません。
基準2:「いつか使う」は使わない(3年ルール)
「いつか使うかも」――。これが、家を散らかす最大の原因です。
しかし、「いつか」は、ほとんどの場合、やってきません。
3年ルールを導入しましょう。
「3年間、一度も使っていないものは、今後も使わない」
これを基準に、以下のものを見直しましょう。
見直し対象リスト
- キッチン家電(ホームベーカリー、たこ焼き器、フードプロセッサー等) → 3年使っていなければ、今後も使いません。
- 食器・調理器具 → 来客用の食器も、実際に年に何回使っているか確認。使っていなければ処分。
- スポーツ用品(スキー板、テニスラケット、ゴルフクラブ等) → 「また始めたい」と思って何年も経っているなら、処分。本当に始めたくなったら、その時また買えます。
- 趣味の材料・道具(裁縫道具、手芸材料、DIY工具等) → 「作りたい」と思っているだけで、3年動いていないなら、その趣味は終わっています。
- 本・雑誌 → 3年読んでいない本は、今後も読みません。電子書籍で買い直せる時代です。
判断のコツ
「もったいない」という気持ちは、一旦横に置きましょう。
使わないものを家に置いておくことが、一番「もったいない」のです。スペースは有限です。
基準3:デジタル化できるもの
現代は、多くのものがデジタル化できる時代です。
物理的なスペースを取らず、検索もしやすく、劣化もしない。デジタル化できるものは、積極的にデジタル化しましょう。
デジタル化すべきもの
□ 書類
- 取扱説明書→メーカーサイトからダウンロード可能
- 保証書→写真で撮影(期限切れのものは処分)
- レシート・領収書→会計ソフトやアプリで管理
- 年賀状・手紙→写真で撮影
- 子どもの学校プリント→スマホで撮影
□ 写真・アルバム
- 古い写真→スキャンアプリで取り込み
- ネガフィルム→写真店でデジタル化サービス利用
- アルバム→写真だけ取り出してスキャン、アルバム本体は処分
□ CD・DVD・ビデオテープ
- 音楽CD→サブスク音楽サービスに移行
- DVD→デジタル版を購入、またはサブスク動画サービスで視聴
- ビデオテープ→ダビングサービスでデジタル化
□ 本・雑誌
- 再読する可能性がある本→電子書籍で買い直し
- 資料として取っておきたい部分→スマホで撮影
実践のポイント
デジタル化したデータは、必ず複数の場所にバックアップしましょう。
- クラウドストレージ(Google Drive、iCloud等)
- 外付けハードディスク
- USBメモリ
最低でも2箇所、できれば3箇所に保存しておくと安心です。
基準4:サイズが合わなくなった服
40代は、体型が変わる時期でもあります。
「痩せたら着る」「また流行るかも」と取っておいた服が、クローゼットを占拠していませんか?
処分すべき服の基準
- サイズが合わない服(1年以内に体型が戻る予定がなければ処分)
- 2年以上着ていない服
- 流行遅れのデザイン(「また流行る」は来ません)
- 毛玉、シミ、ほつれがある服(「直して着る」は直しません)
- 「いつか着るかも」と思っている冠婚葬祭服(冠婚葬祭は、その都度買う方が今風)
残す服の基準
- この1年で3回以上着た服
- 着ると気分が上がる服
- 体型をカバーしてくれる服
- 着回しがきく服
クローゼットの原則は、**「今の自分が、今着たい服だけ」**です。
基準5:壊れた家電・古いケーブル類
「まだ使えるかも」「修理すれば」と思いながら、放置していませんか?
すぐに処分すべきもの
- 壊れた家電(修理費用を考えると、新品を買った方が安い)
- 古いケーブル類(何のケーブルか分からないものは、絶対使いません)
- 古いスマホ・タブレット(データを消去して、回収ボックスへ)
- 使わないACアダプター・充電器(対応機器がないなら不要)
- 古いパソコン・周辺機器(セキュリティリスクもあるので処分)
実践のポイント
家電は、自治体の回収、家電量販店の回収サービス、不用品回収業者を利用しましょう。
小型家電(ケーブル類、スマホ等)は、家電量販店や自治体の回収ボックスが便利です。
これらの基準を使って、少しずつ「捨てどき」を判断していきましょう。
一度に全部やる必要はありません。週末に1カテゴリずつ、進めていけば大丈夫です。
「防災×介護×老後」を見据えた収納
40代の今、整理する目的は、「スッキリした部屋にする」だけではありません。
「防災」「介護」「自分の老後」――この3つを見据えた収納を作ることが、最も重要なのです。
重要書類ボックスの作成
まず最初に作るべきは、**「緊急時に持ち出せる重要書類ボックス」**です。
災害時、急な入院時、親の介護が始まった時――。様々な「もしも」の時に、すぐに必要な書類を取り出せる状態にしておきましょう。
自分用の重要書類ボックス
A4サイズのファイルボックスを用意し、以下を収納します。
□ 身分証明関連
- 健康保険証のコピー
- 運転免許証のコピー
- マイナンバーカードのコピー
- パスポートのコピー
□ 金融関連
- 銀行通帳の表紙のコピー(口座番号が分かるもの)
- キャッシュカード・クレジットカードのリスト
- 印鑑(銀行印・実印)
- 保険証書(生命保険、医療保険、火災保険等)
□ 不動産・契約関連
- 不動産権利証・登記簿のコピー
- 賃貸契約書(賃貸の場合)
- 住宅ローン契約書
- 携帯電話、光熱費等の契約書
□ 医療・健康関連
- お薬手帳のコピー
- 診察券のリスト
- かかりつけ医の連絡先
- 既往歴・アレルギー情報
□ 家族関連
- 戸籍謄本のコピー
- 年金手帳のコピー
- 子どもの健康保険証のコピー
□ その他
- 緊急連絡先リスト(家族、親戚、友人、職場)
- パスワード管理リスト(銀行、各種サービス)※家族が見ても分かるように
- エンディングノート(延命治療、葬儀、財産等の希望)
親用の重要書類ボックス
同様に、親の重要書類も、あなたの家に1セット用意しておきましょう。
- 親の保険証・診察券のコピー
- 親の通帳情報(口座番号、銀行名)
- 親のかかりつけ医リスト
- 親の服薬リスト
- 親の緊急連絡先(兄弟姉妹、親戚、ケアマネージャー等)
保管場所のルール
重要書類ボックスは、以下の場所に保管します。
- 玄関近く、または寝室(避難時にすぐ持ち出せる)
- 家族全員が場所を知っている
- 防水ケースに入れる(災害時の水濡れ対策)
そして、年に1回、内容を見直す習慣をつけましょう。(誕生日、正月等、決めた日に)
緊急避難時に持ち出せる荷物量に
防災の観点から、「本当に必要なものだけ」に絞ることも重要です。
災害時、持ち出せる荷物の量は限られています。
- 一人当たり、リュック1つ分が目安
- 重さは、10kg以内(女性は5〜7kg)
あなたの家には、この基準をクリアできるだけの「最低限のもの」がありますか?
もし家中がモノであふれていると、「何を持ち出すか」の判断すらできません。
日常的にモノを減らしておくことが、災害時の命を守ることにつながるのです。
防災リュックの中身(最低限)
参考までに、防災リュックに入れるべきものをリストアップします。
- 水(500ml×3本程度)
- 非常食(3日分)
- 懐中電灯・ラジオ
- モバイルバッテリー
- 救急セット
- 常備薬・お薬手帳
- マスク・消毒液
- 下着・靴下の替え
- タオル・ウェットティッシュ
- 重要書類ボックス
- 現金(小銭も)
- ホイッスル
将来バリアフリー化しやすい配置
40代の今、自宅の配置を見直す際は、**「将来、自分が介護される側になる」**ことも想定しましょう。
廊下・動線の確保
- 廊下の幅:80cm以上(車椅子が通れる)
- 段差の解消(将来、スロープを設置できるスペース)
- 手すりの設置スペース(壁に家具を置きすぎない)
寝室の配置
- ベッド周りに60cm以上のスペース(介護者が立てる)
- ベッド→トイレの動線にモノを置かない
- 照明スイッチが、ベッドから手が届く位置
浴室・トイレ
- 浴室に椅子を置けるスペース
- トイレに手すりを設置できる壁
- ドアは引き戸、または外開き(中で倒れた時に開けられる)
これらを今すぐ全て変える必要はありません。しかし、「家具を置く時」「模様替えする時」に、この視点を持つだけで、将来の負担が大きく変わります。
介護用品を置くスペースの確保
親の介護が始まると、以下のようなものが、あなたの家に増えます。
- おむつ、尿取りパッド(ストック)
- 介護用の衣類、タオル
- 車椅子(折りたたみ式でも、そこそこ大きい)
- 歩行器、杖
- ポータブルトイレ(在宅介護の場合)
**最低でも、1畳分(押し入れの半分、またはクローゼットの一角)**は、空けておきましょう。
「今はモノでいっぱいだから無理」
そう思うなら、今こそ、整理を始めるタイミングです。
「防災×介護×老後」を見据えた収納は、決して「縁起でもない」話ではありません。
未来の自分を助ける、最高の投資なのです。
家族を巻き込む整理術
ここまで、あなた自身ができる整理術をお伝えしてきました。
しかし、家の整理は、あなた一人の問題ではありません。家族全員で取り組むべき課題です。
特に、親の介護が始まった時、「家族が協力できるか」が、介護生活の成否を分けます。
夫・子どもにも「モノの場所」を共有
「お母さん、○○どこ?」
この質問に、毎日何回答えていますか?
家の中のモノの場所を知っているのが、あなただけなら、それは危険信号です。
あなたが倒れた時、家族は生活できません。
共有すべき「モノの場所」リスト
以下の場所を、家族全員が把握できるようにしましょう。
□ 重要書類
- 保険証、診察券
- 通帳、印鑑、キャッシュカード
- 各種契約書
□ 日用品のストック
- ティッシュ、トイレットペーパー
- 洗剤、シャンプー
- 電球、電池
□ 薬・救急箱
- 常備薬
- 絆創膏、消毒液
- 体温計、血圧計
□ 防災用品
- 懐中電灯
- 非常食
- カセットコンロ
□ 工具・メンテナンス用品
- ドライバー、ペンチ
- ガムテープ、接着剤
- 電球、ヒューズ
実践方法
方法1:ラベリング
収納ケース、引き出し、棚に、中身が分かるラベルを貼りましょう。
「救急箱」「工具」「電池・電球」等、一目で分かるように。
方法2:「モノの地図」を作る
家の見取り図に、「どこに何があるか」を書き込んだ「モノの地図」を作り、家族で共有します。
スマホで撮影して、家族全員に送信しておくのもおすすめです。
方法3:「探させる」習慣をつける
「○○どこ?」と聞かれたら、すぐに答えるのではなく、
「リビングの棚だよ」「玄関の靴箱の上だよ」
と、場所だけ伝えて、自分で探させる習慣をつけましょう。
最初は面倒ですが、これを続けることで、家族は自然に「モノの場所」を覚えていきます。
「もしもノート」の作成
エンディングノートは、高齢者だけのものではありません。
40代のあなたにも、**「もしもノート」**が必要です。
もしもノートに書くべきこと
□ 基本情報
- 本籍地、血液型、持病、アレルギー
- かかりつけ医、服用中の薬
□ 緊急連絡先
- 家族、親戚
- 職場の上司、同僚
- 親しい友人
□ 財産・契約情報
- 銀行口座(銀行名、支店名、口座番号)
- クレジットカード
- 保険(生命保険、医療保険、火災保険等)
- 不動産
- ローン、借入
- サブスクサービス(自動引き落としされているもの)
□ パスワード情報
- 銀行のオンラインバンキング
- 各種サービスのID・パスワード
- スマホ・パソコンのロック解除方法
□ 医療・介護の希望
- 延命治療を希望するか
- 臓器提供の意思
- 終末期医療の希望
□ 葬儀・お墓の希望
- 葬儀の規模、形式
- お墓の場所
- 遺影に使ってほしい写真
□ 家族へのメッセージ
- 夫へ
- 子どもへ
- 親へ
- 兄弟姉妹へ
保管方法
もしもノートは、以下の場所に保管し、家族に伝えておきましょう。
- 重要書類ボックスの中
- 家族が知っている場所
- 弁護士や信頼できる第三者に預ける(希望の場合)
そして、年に1回、内容を見直し、更新しましょう。
月1回の「整理デー」習慣化
最後に、最も重要な習慣をお伝えします。
それは、「月に1回、家族で整理をする日」を決めることです。
整理デーの進め方
日時を固定する
- 「毎月第1日曜日の午前中」等、決まった日時に設定
- カレンダーに記入し、家族全員が予定を空ける
役割分担をする
- 夫:書類整理、粗大ゴミの運び出し
- あなた:キッチン、衣類、日用品
- 子ども:自分の部屋、学用品
テーマを決める
- 「今月はクローゼット」「今月は書類」等、毎月テーマを決める
- 一度に全部やろうとしない
処分リストを作る
- 「今月処分したもの」をリスト化
- 達成感を共有する
ご褒美を用意する
- 整理が終わったら、家族で外食、映画鑑賞等
- 楽しみがあると、続けやすい
家族会議も同時開催
整理デーの後に、**「家族会議」**も開きましょう。
- 今月の予定確認(学校行事、仕事、帰省等)
- 親の様子(最近の連絡内容、健康状態)
- 家計の確認(必要な出費、貯金目標)
- 困っていること、相談したいこと
月に1回、家族で話す時間を持つことで、いざという時にも、スムーズに協力できる関係が築けます。
親の介護は、突然やってきます。
その時、「家族がバラバラ」では、乗り越えられません。
今から、家族で協力する習慣を作っておくこと。
それが、未来の自分と家族を救う、最大の備えなのです。