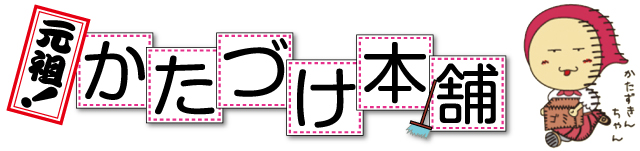第4章:【実践編】タイムライン別行動計画
ここまで、実家と自宅、それぞれの整理術をお伝えしてきました。
しかし、「何から始めればいいのか分からない」「全部やるのは無理」と感じている方も多いでしょう。
大丈夫です。一度に全部やる必要はありません。
この章では、「今すぐ〜1年後」まで、具体的な行動計画をタイムライン形式でお伝えします。あなたのペースで、一つずつ進めていきましょう。
今すぐ〜3ヶ月:最優先タスク
まずは、**「今すぐやるべきこと」**から始めましょう。
この期間の目標は、「緊急時に困らない最低限の準備」です。
Week 1-2:情報収集と対話の準備
□ 親の健康状態を確認する
- 電話やLINEで、最近の体調を聞く
- 「最近、物忘れが増えた」「足腰が弱くなった」等の変化がないかチェック
- かかりつけ医の名前と連絡先を確認
□ 次の帰省日を決める
- お盆、正月、連休等、実家に帰る日程を確定
- 「片付けを手伝いたい」と事前に伝えておく(急に言うと警戒される)
□ 自宅の現状を把握する
- この章の最初の「診断チェックリスト」を実施
- 改善が必要な項目をリストアップ
□ 家族で話し合う
- 夫や子どもに、「親の介護が始まるかもしれない」ことを伝える
- 家族で協力する必要があることを共有
- 反発されても、焦らず、少しずつ理解を求める
Week 3-4:実家の重要書類確認
□ 帰省時、または電話で確認する項目
「お母さん、もしもの時に困らないように、大事なものの場所を教えてくれる?」
そう切り出して、以下を確認します。
- 健康保険証、診察券の保管場所
- 通帳、印鑑、キャッシュカードの保管場所
- 不動産の権利証の場所
- 生命保険、医療保険の証書
- 遺言書の有無
- かかりつけ医の連絡先
- 服薬中の薬のリスト
□ 「緊急連絡先リスト」を作成
親と一緒に、A4用紙1枚に、以下をまとめます。
- かかりつけ医(病院名、電話番号、担当医師名)
- かかりつけ薬局
- 兄弟姉妹の連絡先
- 親しい友人・近所の人の連絡先
- あなた(娘)の連絡先(職場、携帯)
このリストは、冷蔵庫に貼る、または電話の近くに置くことで、緊急時にすぐ使えます。
□ 情報を持ち帰る
確認した情報を、自宅に持ち帰り、「親用の重要書類ボックス」に保管します。
- 保険証のコピー
- 通帳情報(銀行名、支店、口座番号)のメモ
- 緊急連絡先リストのコピー
Week 5-8:自宅の最優先整理
□ 重要書類ボックスを作る
第3章で説明した「自分用の重要書類ボックス」を作成します。
まずは、以下の書類を集めるだけでOK。
- 健康保険証、診察券
- 通帳、印鑑
- 保険証書
- 不動産関係書類
- 契約書類
整理は後回しで構いません。まずは「1箇所に集める」ことが重要です。
□ 「1年使わなかったモノ」30個処分
家中を見渡して、「1年使っていないもの」を30個、ピックアップして処分します。
ルール:1日1個でOK(30日で達成)
- 壊れたボールペン
- 期限切れの調味料
- 着ていない服
- 読まない雑誌
- 使わないバッグ
- 子どもが遊ばないおもちゃ
- 古いケーブル
- 化粧品のサンプル
- 期限切れのクーポン券
- 引き出しの奥の「何か分からないもの」
最初は簡単なものから。小さな達成感を積み重ねることが、継続のコツです。
□ 玄関と廊下の動線確保
家族全員が毎日通る場所を、まず整えます。
- 玄関の靴を減らす(1人3足まで、残りは下駄箱へ)
- 廊下に置いているモノを撤去
- 床に這っている電気コードを整理
□ プロの見積もり依頼(必要なら)
もし実家が以下の状態なら、この段階でプロに見積もりを依頼しましょう。
- 一軒家で、モノが大量にある
- ゴミ屋敷・汚部屋化している
- 親が認知症で、判断ができない
- 遠方で、頻繁に通えない
見積もりは無料の業者を選び、まずは現状を把握することが目的です。
Week 9-12:継続と習慣化
□ 月1回の「整理デー」を開始
第3章で説明した「月1回の整理デー」を、実際に始めます。
最初のテーマは、**「書類整理」**がおすすめです。
- 郵便物の整理
- 不要なダイレクトメールの停止手続き
- 古い領収書の処分
□ 親との定期連絡を習慣化
週に1回、電話やLINEで親と連絡を取る習慣をつけます。
- 体調の確認
- 困っていることがないか
- 次に帰省する日程の相談
□ 達成したことをリストアップ
3ヶ月でできたことを書き出し、自分を褒めましょう。
「重要書類の場所が分かった」 「30個、モノを減らせた」 「家族で話し合う機会ができた」
小さな進歩でも、確実に前進しています。
3ヶ月の成果チェック
□ 親の重要書類の場所を把握した □ 自宅に親用の情報ボックスを作った □ 自宅の重要書類を1箇所に集めた □ 30個以上、モノを処分した □ 家族で「もしもの時」について話し合った □ 月1回の整理デーを始めた
3つ以上達成できていれば、上出来です!
3〜6ヶ月:安全と仕組みづくり
次の3ヶ月は、**「安全な生活空間」と「継続できる仕組み」**を作る期間です。
Month 4:実家の動線確保
□ 帰省時、親と一緒に安全チェック
「お母さん、この廊下、モノが多くて危ないよ。一緒に片付けようよ」
そう声をかけて、以下の場所を整理します。
□ 玄関
- 靴の数を減らす(1人5足まで)
- 傘立てを整理
- 新聞や郵便物を溜めない仕組み作り(すぐ処分する習慣)
□ 廊下
- 床に置いているモノを撤去(段ボール、古新聞等)
- 電気コードの固定
- 夜間用の足元灯を設置
□ 階段
- 手すりの確認(必要なら設置を提案)
- 階段に置いているモノを撤去
- 滑り止めの確認
□ トイレ・浴室への動線
- 脱衣所のモノを減らす
- トイレまでの動線にモノがないか確認
- 浴室マットの滑り止め確認
この作業は、1日で終わらせようとしない。 滞在中、少しずつ進めます。
Month 5:自宅の書類整理とデジタル化
□ 重要書類のファイリング
3ヶ月目に集めた書類を、きちんとファイリングします。
- カテゴリ別(金融、保険、医療、契約、不動産)にクリアファイルで分ける
- インデックスをつける
- A4ファイルボックスに収納
□ 取扱説明書のデジタル化
家電の取扱説明書は、メーカーサイトからPDFをダウンロードし、紙は処分。
どうしても必要なものだけ、1冊のファイルにまとめます。
□ 写真のデジタル化開始
古いアルバムの写真を、少しずつスキャン。
ルール:1日10枚ずつ(無理なく続ける)
スマホのスキャンアプリ(Google フォトスキャン、Adobe Scan等)を使えば、簡単です。
□ 契約の見直し
不要なサブスクサービス、使っていない会員サービスを解約します。
- 動画配信サービス
- 音楽配信サービス
- 雑誌の定期購読
- ジムの会員(1年以上行っていない)
- クレジットカード(使っていないもの)
Month 6:防災備蓄の見直し
□ 防災リュックの作成
第3章で説明した「防災リュック」を、実際に作ります。
家族分(最低でも自分と子ども)のリュックを用意。
□ 非常食の見直し
- 賞味期限切れのものを処分
- 必要な分だけ買い足す(3日分×家族人数)
- ローリングストック(日常で使いながら備蓄)の仕組み作り
□ 避難経路の確認
家族で、以下を確認します。
- 自宅から避難所までのルート(実際に歩いてみる)
- 家族の集合場所(災害時、連絡が取れない場合の待ち合わせ場所)
- 避難時の持ち出し品の置き場所
Month 6:親の「大切なモノリスト」作成
□ 親と一緒に「大切なものリスト」を作る
帰省時、親とゆっくり話す時間を作り、以下を確認します。
「お母さんが大切にしているもの、教えてくれる?」
- 形見として残したいもの(誰に譲りたいか)
- 絶対に捨ててほしくないもの
- 供養が必要なもの(仏壇、人形等)
- 友人に返したいもの(借りているもの)
このリストがあることで、将来の遺品整理が格段に楽になります。
6ヶ月の成果チェック
□ 実家の動線が確保された(玄関、廊下、階段) □ 自宅の重要書類がファイリングされた □ 不要なサブスクを解約した □ 防災リュックを作成した □ 親の「大切なものリスト」ができた □ 月1回の整理デーが習慣化した
ここまでくれば、「もしも」の時も、焦らず対応できます。
6ヶ月〜1年:深掘りと未来への備え
最後の6ヶ月は、**「思い出品の整理」と「もしもの話」**に取り組みます。
この期間は、焦らず、親の気持ちに寄り添いながら進めましょう。
Month 7-9:実家の思い出品整理
□ 写真のデジタル化
親と一緒に、アルバムを見ながら進めます。
「この写真、誰?」「この時のこと、教えて」
思い出話を聞きながら、スキャン。一度に全部やろうとせず、帰省のたびに少しずつ。
□ 手紙・年賀状の整理
- 故人からの手紙は、数枚だけ残す
- 年賀状は直近3年分のみ
- 選別したものを写真に撮り、元は処分
□ 衣類の整理
親の衣類を、一緒に見直します。
- 3年着ていない服は処分対象
- 冠婚葬祭用は、今でも着られるサイズか確認
- 思い出の服(和服、ドレス等)は、写真に撮って記録
□ 食器・調理器具の整理
- 欠けた食器、ひび割れた食器は処分
- 来客用の食器は、実際に使っているか確認
- 重複している調理器具を減らす
Month 10-11:自宅の大型家具見直し
□ クローゼット・押し入れの大整理
- 「3年ルール」で、使っていない服、寝具、バッグを処分
- 季節外の服を圧縮袋に入れる
- 親の介護用品を置くスペース(1畳分)を確保
□ 本・雑誌の処分
- 3年読んでいない本は処分
- 電子書籍で買い直せるものは処分
- 本当に大切な本だけ残す(目安:本棚1つ分)
□ 子ども部屋の見直し
子どもと一緒に、以下を整理。
- 使わないおもちゃ
- サイズアウトした服
- 古い教材、プリント
子どもに「選ぶ力」を教える良い機会です。
□ 大型家具の処分検討
- 使っていない婚礼タンス
- 壊れたソファ
- 古いベッド
粗大ゴミ、リサイクル業者、不用品回収業者を活用します。
Month 12:親との「もしもの話」
これが、最も重要で、最も難しいステップです。
しかし、避けて通れない話でもあります。
□ 延命治療について
「お母さん、もしもの時のこと、聞いておきたいんだけど」
そう切り出して、以下を確認します。
- 延命治療を希望するか
- 回復の見込みがない場合、どうしたいか
- 尊厳死、安楽死についての考え
- 臓器提供の意思
□ 葬儀・お墓について
- 葬儀の規模(家族葬、一般葬)
- 宗派、菩提寺
- お墓の場所、継承者
- 散骨、樹木葬等の希望
□ 財産・相続について
- 預貯金の総額(概算でOK)
- 不動産の名義
- 生命保険の受取人
- 遺言書の有無
- 兄弟姉妹への分配の希望
この話は、一度で終わらせる必要はありません。
少しずつ、親の気持ちを聞きながら、進めましょう。
Month 12:介護保険の事前学習
□ 介護保険制度について学ぶ
親が65歳以上なら、介護保険の対象です。
- 要介護認定の仕組み
- 利用できるサービス(訪問介護、デイサービス、ショートステイ等)
- 自己負担額
- ケアマネージャーの役割
□ 地域包括支援センターの場所確認
親の住む地域の「地域包括支援センター」を調べ、連絡先をメモしておきます。
介護が始まった時、最初に相談する場所です。
□ 介護施設の見学
可能なら、親と一緒に、近くの介護施設を見学。
「将来、もし必要になった時のために」と伝えれば、親も納得しやすいです。
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- グループホーム
見学することで、「介護施設は怖い場所じゃない」と、親も安心します。
1年の成果チェック
□ 実家の思い出品(写真、手紙)の整理が進んだ □ 自宅の大型家具を見直し、スペースが確保できた □ 親と「もしもの話」ができた □ 介護保険について学んだ □ 地域包括支援センターの場所を確認した □ 月1回の整理デーが、家族の習慣になった
ここまでできれば、あなたは素晴らしいです!
継続すること:1年後も続けるべき習慣
1年間、お疲れさまでした。
しかし、整理は「1回やったら終わり」ではありません。継続することが、最も重要です。
年2回の実家チェック(帰省時)
□ お盆と正月、必ず帰省する
どんなに忙しくても、年2回は実家に帰り、以下を確認します。
- 親の健康状態(体調、物忘れの有無、歩行の様子)
- 家の中の安全性(動線、転倒リスク)
- 冷蔵庫の中身(期限切れ食品の増加は、認知症のサイン)
- 郵便物の溜まり具合(片付けられなくなっていないか)
□ 必要に応じて整理を進める
帰省のたびに、少しずつ整理を進めます。
「今回は寝室」「今回は押し入れ」等、テーマを決めて。
月1回の自宅整理デー
□ 整理デーを継続
月1回の整理デーは、家族の習慣として定着させましょう。
- 第1日曜日の午前中(例)
- テーマを変えながら(クローゼット、書類、キッチン等)
- 家族で役割分担
- 終わったらご褒美(外食等)
□ 増やさない工�
整理は、「減らす」だけでなく、**「増やさない」**ことも重要です。
- 「1つ買ったら、1つ捨てる」ルール
- 安いからといって、ストックを買いすぎない
- 無料でもらえるものを、安易にもらわない(ノベルティ、試供品等)
家族との情報共有アップデート
□ 年1回、「もしもノート」を更新
- 連絡先の変更
- 契約内容の変更
- パスワードの変更
- 健康状態の変化
□ 年1回、重要書類ボックスの見直し
- 期限切れの保険証書
- 解約した契約書
- 不要になった書類
□ 親の情報も定期更新
- 親の健康状態
- 服薬内容
- かかりつけ医の変更
- 銀行口座の変更
1年後のあなたへ
1年前、この記事を読み始めた時、あなたは不安だったかもしれません。
「実家も自宅も散らかっている」 「何から始めればいいか分からない」 「親が協力してくれるか分からない」
しかし、1年後の今、あなたは確実に変わっています。
- 実家の重要書類の場所が分かる
- 親の健康状態を定期的に確認している
- 自宅が整理され、家族が協力するようになった
- 「もしも」の時の準備ができている
これは、未来のあなたと家族を救う、最高の投資でした。
そして、この習慣を続けることで、あなたは「介護が始まっても、パンクしない準備」ができているのです。
次の章では、「それでも自分たちでは難しい」という時のために、プロの力を借りる方法を詳しく解説します。